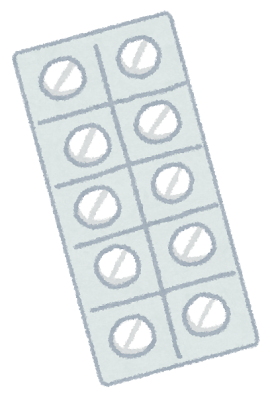薬はどうやって効くの?そしてなぜ副作用が出るの?
「この薬、本当に効いてるの?」「どうして副作用なんてあるの?」
薬を飲んでいると、そんな疑問を持ったことはありませんか?
実はこの“なぜ?”には、ちゃんと理由があるんです。
薬は病気を治すためのものですが、実際には“体の中でどんな働きをしているのか”を知る機会は意外と少ないものです。
今日は、薬が効く仕組みと、副作用が起きる理由をお話しします。
●薬が効くってどういうこと?
薬は、体の中の「特定の場所」にくっついて効果を発揮します。
その場所は「受容体(じゅようたい)」と呼ばれ、薬の成分はその鍵穴に合う“鍵”のようなものです。
この鍵と鍵穴が合うことで、体の反応を変化させるのです。
たとえば、解熱鎮痛薬(げねつちんつうやく)は、脳にある「体温を調整するスイッチ」に働きかけて熱を下げます。
咳止めの薬なら、咳の反射を起こす神経に作用して落ち着かせます。
つまり薬は、体の中で“必要なスイッチを押す”ことで効果を出しているんです。
魔法ではなく、体の仕組みをそっと助けてくれる存在なんですよ。
● じゃあ副作用はなぜ出るの?
薬は“ピンポイント”で効くように作られていますが、体の中はとても複雑です。
そのため、狙った場所だけでなく、似たような仕組みを持つ他の部分にも影響してしまうことがあります。
たとえば、花粉症などで使う「抗ヒスタミン薬」は、鼻水やくしゃみを止めるためにヒスタミンという物質をブロックします。
ところがこのヒスタミン、脳でも“目を覚ます”働きをしているんです。
そのため、薬が脳にも少し作用して「眠くなる」という副作用が出るんですね。
また、体質・年齢・他の薬との飲み合わせなどによっても、反応は変わります。
だからこそ、薬剤師は患者さんごとに副作用が出やすい条件を確認しているんです。
●薬剤師として伝えたいこと
副作用というと「怖いもの」と感じるかもしれません。
でも実はそれ、薬が“確かに体で働いている証拠”でもあります。
「ちょっと眠くなる」「胃が重く感じる」――そんな反応も、
薬が体の中で頑張っているサインかもしれません。
大切なのは、「必要な効果をしっかり出しつつ、不要な作用をできるだけ減らすこと」。
そのバランスを取るのが、薬剤師の大事な役割です。
●まとめ
薬は「毒にも薬にもなる」化学物質。
正しく使えば、体を助ける強い味方です。
「なぜ効くのか」「なぜ副作用が出るのか」を少しでも知ってもらえたら、
薬への不安が減り、安心して服用してもらえると思います。
薬は日常の中で使う大切なもの。
気になることがあれば、遠慮せず薬剤師に聞いてくださいね。